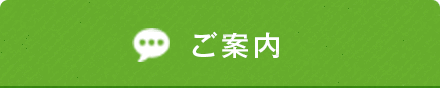東松島市宮戸地区の奥松島果樹生産組合いちじくの里は2月9日、東日本大震災の津波被害を受けた農地で栽培している桃の収量向上に向けて、果樹栽培講習会を開きました。2016年4月に、1㌶で140本を定植した桃「くにか」と「まどか」の2品種の剪定、防除方法を学ぼうと組合員ら12人が参加しました。桃の栽培は今年で3年目を迎えます。
福島県で桃農家を営む遠藤道夫氏を講師に招き、剪定作業を実演しました。遠藤氏は、開花前に見られがちな、病害の防除法と、葉芽と花芽の見分け方や、重なり枝などの幼木の剪定方法を説明し「生育は順調で、組合員たちの剪定もよくできている。残す枝を見極めて、開花前の防除をていねいに行い、日光をたくさん浴びせること」と話し、春先の雨天によって広がりがちな病害虫に注意することを呼び掛けました。
その後、石巻農業改良普及センターの鵜飼真澄氏が、栽培暦を用いて、開花前の時期に見られやすい、せん孔細菌感染症やシンクイムシなどの病害虫対策について話しました。圃場(ほじょう)の周囲に暴風ネットを設置し早期に除去することや、5月から7月にかけて予防剤の散布をすることが大切だと呼び掛け、実例を写真で説明しました。
昨年は、収穫した桃の7割がハクビシンや猿の食害に遭ったことから、害獣対策について話し合い、猿避けネットの設置や圃場(ほじょう)の巡回など、地域住民とも協力し一丸となって対策をしていきます。
同組合の尾形善久組合長は「剪定作業も組合員全員で、より良い手段を相談しながら共に行ってきた。害獣による食害が深刻なので、対策を模索し収量を増やしていきたい」と意気込みを話しました。
昨年の収穫量はおよそ1000個でしたが、今年は防除と害獣対策に力を入れ、3000~3500個の収穫を目指し、販売高の向上を狙います。農地ではこのほか、2㌶でイチジクと柿を栽培。今後は地域ぐるみで観光農園としての活用も検討しています。
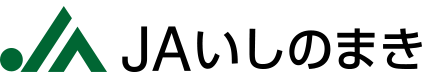




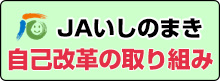





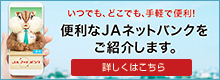
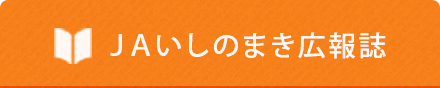
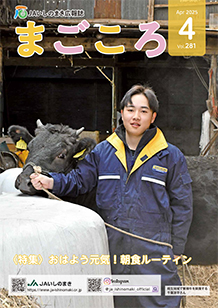 JAいしのまきでは、組合報「まごころ」を毎月発行しております。
JAいしのまきでは、組合報「まごころ」を毎月発行しております。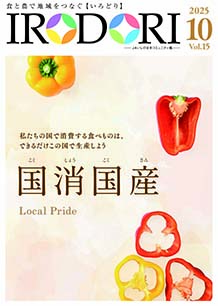 地域住民の皆さんにさまざまな情報をお届けするコミュニティ紙「IRODORI」を発行しています。
地域住民の皆さんにさまざまな情報をお届けするコミュニティ紙「IRODORI」を発行しています。